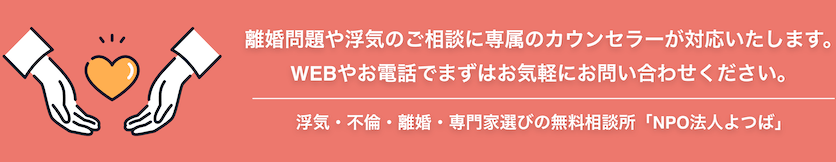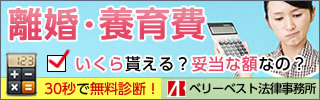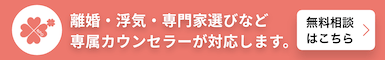減らされてしまう条件は?養育費の減額請求を受けたときの対処法
離婚時に合意した養育費でも、月日が経つと相手方から「減額したい」と言われることが。
養育費を減らされてしまうと生活が苦しくなるため、どうにかして回避できないかと悩んでしまいますよね。
そもそも、どのようなときに養育費の減額が可能なのでしょうか。
そこで、養育費の減額請求があったときの適切な対処方法を紹介します。
養育費は減額できる

離婚前に何度も話し合って決めたはずの養育費。
調停で取り決めをしたにもかかわらず、一方的に減額を迫られると「話が違う」と感じてしまうでしょう。
ただ、養育費はいくつかのケースに当てはまると減額が認められています。
そこで、まずは減額請求が認められるケースについて解説しましょう。
受け取る側が再婚をして子どもが再婚相手の養子になった
養育費を受け取っている側が再婚した場合、養育費が減額できる可能性が高くなります。
この場合、再婚相手と子どもが養子縁組をしていることが条件です。
これは、養子縁組によって再婚相手が子どもの第1次的な扶養義務者になるためです。
支払う側の扶養義務が軽くなることから、再婚相手の年収に応じて減額が認められる場合があります。
受け取る側の収入が増えた
離婚時にはパートとして働いていても、正社員として働きだしたり、ビジネスが成功したりといった理由で受け取る側の収入が増えることがあるでしょう。
この場合、減額が認められることがあります。
ただし、はじめから受け取る側の収入が増えることを想定して養育費を取り決めた場合の減額は難しいといえます。
支払う側の収入の減少
支払う側が務めている会社が倒産したり、リストラに遭って転職をしたりといった場合には、収入が減ってしまうことがあるでしょう。
また、思いがけないケガや病気により働けなくなることも考えられます。
このように、支払う側の収入の大幅な減少や、収入自体がなくなってしまった場合には減額となる可能性が高いでしょう。
支払う側の扶養家族が増えた
支払う側が再婚をして配偶者ができたり子どもができたりすると、減額請求が認められる可能性があります。
また、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合にも、減額が認められやすいでしょう。
これは、扶養家族が増えることで経済的な負担が増大し、子ども1人あたりにかけられる費用が減ることが理由です。
こんな場合には認められない

支払う側に経済的な問題が生じて支払いが難しくなった場合や、受け取る側の経済力が向上した場合には減額が認められやすいでしょう。
ただ、次の場合には養育費の減額が認められにくくなるため注意が必要です。
受け取る側が再婚をしても子どもは養子縁組をしていない
養育費を受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合、再婚相手に子どもの扶養義務が発生しません。
よって、養育費の減額は難しくなります。
相場より金額が高いことがわかった
養育費には相場があり、相場をもとに話し合って金額を決めるのが一般的です。
しかし、離婚前の話し合いの時点で相場を知らなかった場合、相場より高い金額で取り決めをしたことに後から気づくこともあるでしょう
しかし、一旦納得した金額ですので、「やっぱり払いすぎていた」という理由では減額が認められにくいといえます。
これは、合意したほうにも責任があると考えられているからです。
子どもとの面会交流が実現していないことが理由
離婚時には、子どもとの面会交流についても取り決めが行われます。
「月に1回は面会する」と決められていても、都合が合わなかったり、子どもが会いたがらなかったりという理由で面会交流が実現しないことがあるでしょう。
毎月養育費を支払っているのに子どもと会えない状態が続くと、養育費を減額したいと言い出すケースが少なくありません。
しかし、養育費は子どもに面会するための交換条件ではないのです。
養育費と面会交流はぞれぞれ別の取り決めですので、面会できないことが養育費の減額の理由にはならないと考えましょう。
減額請求で不利にならないポイント

養育費の支払い側から減額請求があったとき、相手に主導権を握られると不利な結果になることは多いでしょう。
離婚をした相手とのトラブルは面倒なため、できるだけ避けたいものです。
トラブルを回避しつつできるだけ有利に交渉が進められるよう、これから紹介するポイントを押さえておくのをおすすめします。
相場を理解しておく
養育費の減額を請求されたとき、その金額が妥当かを瞬時に判断するのは難しいものです。
そのため、話し合いの場に出向く前に養育費の相場を理解しておくのがよいでしょう。
そうすることで、相場とかけ離れた金額を主張してしまったり、相手の意見を鵜呑みにしてしまったりといった問題が防げます。
また、相場がわかっていると落ち着いてスムーズに話し合いが進められる点もメリットです。
計算に自信がないという場合には、弁護士に相談をして正しく計算してもらうのも1つの方法ですね。
養育費の相場を計算するのに役立つ算定表はこちらからも確認できます。
養育費算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
主張を裏付ける証拠集めをする
離婚後に収入が少なく経済的に苦しいという状況や、子どもが再婚相手と養子縁組をしていないことなどを相手に主張できると、養育費の減額請求は認められにくいでしょう。
ただし、口頭でどれだけ説明をしても信じてもらうのは難しいため、主張を裏付けられる証拠を集めておくのがおすすめです。
給与明細や課税証明書、戸籍謄本なども証拠になりますので準備しておきましょう。
養育費の減額を請求されたときにすべきこと

養育費の支払い側から急な減額請求を突き付けられても、すぐに返事をするのではなく、やむを得ない事情かどうかをしっかりと考えましょう。
もし、やむを得ない事情がないと感じるのであれば、「養育費減額には応じられない」ときっぱりと反論します。
話し合いで解決しない場合には家庭裁判所での調停となり、それでも決着がつかないときには裁判官による審判となるでしょう。
養育費減額請求はこじれやすいため、泥沼化しないためにもコツを抑えて早めに解決するのがおすすめです。
ここからは、それぞれのシーンにおける注意点を紹介します。
まずはじっくり話し合う
離婚をした相手と養育費について話し合うのは楽しいものではないでしょう。
しかし、話し合いで解決できると、調停などの面倒な手続きが必要なく、円満に解決しやすくなります。
ただし、お金が絡む話し合いが簡単に解決するとはいいがたいため、交渉が長引く可能性があると覚悟しておきましょう。
また、今後調停になることも考え、悪い印象を与える言動は避けるのがベターです。
感情的にならず、減額に応じられない理由についても明確に伝えることが大切になります。
話し合いで養育費の減額や変更日などがまとまった場合には、将来的なトラブルを避けるため、強制執行受諾文言付きの公正証書を作成しておくのがおすすめです。
家庭裁判所での養育費減額請求調停
話し合いだけではまとまらない場合には、家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立てます。
養育費減額請求調停は当事者の間に調停委員や裁判官が入り、解決策を探る場所です。
1回目の調停が終わると2回目の調停の日にちが指定されますが、1回目から1か月後ということが多いでしょう。
2回目で決まらず、3回目、4回目となるとそれだけ時間がかかりますので、できるだけ早く解決策を見つけるのがおすすめです。
調停は双方が合意に至るまで続けられることもありますが、これ以上話しても合意には至らないと判断されたときには調停不成立となります。
調停が不成立になった場合は自動的に教育費減額審判に移動し、裁判官による審判を受ける流れです。
裁判官による審判で決まった金額は守らなければなりません。
養育費減額審判
調停では双方の話し合いで養育費の減額問題を解決しますが、審判は裁判官によって判断が下されます。
非公開で行われる審問や、家庭裁判所による事実調査の資料をもとに養育費を減額すべきかを判断されるのです。
調停の段階で必要な資料がそろっていれば1~2カ月で審判が出ることがありますが、資料がそろわないなどの理由で長くかかることもあるでしょう。
一方的な養育費の減額はできない

離婚時に取り決めた養育費を勝手に減額することは認められません。
しかし、経済的な問題を理由に支払う側から一方的に減額されたり、未払いにされたりすることはめずらしくないのです。
相手方から一方的に養育費を減額されたり、未払いになったりといったトラブルが生じたときは、まず話し合い、調停、審判という手順を踏んで解決しましょう。
相手方が話し合いに応じない場合、作成した取り決めが債務名義によるものであれば強制執行という方法もあります。
養育費の取り決めが強制執行受諾文言付きの公正証書や、調停証書、審判書などであれば相手方の預金口座などの差し押さえが可能です。
その結果、取り決め通りに養育費が受け取れるようになります。
債務名義とは
養育費を受け取る側が支払う側に対して強制執行を許可する公的な書類を債務名義といいます。
債務名義があることで相手方の財産を差し押さえられるようになり、未払いの養育費を回収できます。
構成執行受諾文言付きとは
養育費を支払う側が養育費を支払わなかった場合、強制執行を受け入れるという文言が付けられたものをいいます。
構成執行受諾文言付きの公正証書は債務名義となるため、養育費が一方的に減額された場合でも、強制執行が可能です。
条件によっては合意も視野に

養育費は、子どもの人数と年齢、元夫婦の年収によって決められます。
離婚時には元気に仕事ができていても、突然の病気やケガで仕事を辞めなければならない日が来ることもあるでしょう。
また、会社が急に倒産したり、ビジネスがうまくいかなくなることもあります。
そういった場合には「約束をしたから」と養育費の減額を拒否し続けるのではなく、話し合いに応じるのも1つの方法です。
離婚したとはいえ子どもにとっては両親ですので、養育費でいがみ合っている姿を見たくないでしょう。
正当な理由がある場合には相手方の立場を理解するのも1つの解決策といえます。
弁護士に相談すると安心

離婚した相手から養育費の減額請求があり、話し合いがこじれた場合には調停が申し立てられることがあるでしょう。
そうなると、離婚のときのように精神的にも肉体的にも疲れてしまう可能性が高くなります。
また、自分一人で立ち向かった場合には、減額を拒否できる正当な理由をうまく伝えられなかったり、元夫の強い主張に飲まれてしまうことも考えられるでしょう。
離婚した相手とのトラブルを避け、養育費の減額問題を乗り越えるには弁護士などの専門家に相談をするのが安心です。
弁護士は法律の専門家でありこれらの問題解決のプロですので、上手なやり方で養育費の減額を食い止めてくれる可能性が高くなります。
ただし、弁護士に相談をする場合にはお金が必要です。
成功報酬も必要となり、結果的にお金がかかりすぎることもあるでしょう。
そのため、まずは信頼できる場所に相談するのをおすすめします。
NPO法人よつばに相談を

一方的に養育費の減額を請求されたり、養育費減額調停の申し立てを行われた場合には、不安だけが募ります。
また、離婚した相手と再度やりあうのかと考えるとストレスも感じてしまうでしょう。
ひとりで問題を抱えると精神面や体調に支障をきたすこともありますので、信頼できる誰かに相談するのをおすすめします。
周囲に相談できる人がいないという場合は、NPO法人よつばに相談をしてみてはいかがでしょうか。
こちらでは離婚や養育費に関する相談を無料で受け付けています。
誰かに話すだけでも気持ちが軽くなりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
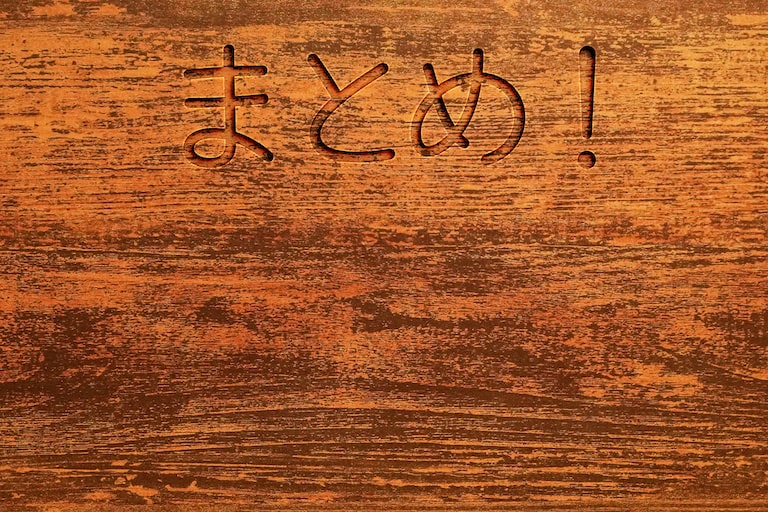
養育費は双方の話し合いによって減額が可能です。
ただし、減額が認められる条件がいくつかありますので、相手の立場や状況を理解して話し合うのがよいでしょう。
また、一方的な養育費の減額は認められておらず、支払う側から勝手に減額された場合には強制執行の申し立ても可能です。
取り決めたはずの養育費の減額請求に困っているのであればNPO法人よつばにご相談ください。
悩みを聞いてもらうことで、解決への糸口が見つかる可能性があります。