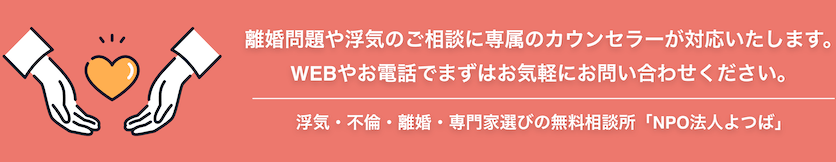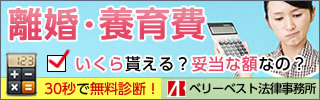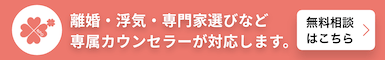近年のDV相談件数の推移と支援窓口のNPO法人よつばを紹介
コロナ禍の影響でDV被害者が増え、各地の支援機関に寄せられるDV相談件数も10万件を超えるようになり、社会問題となっています。
ここでは、DV相談件数のデータを示すとともに、支援機関の利用法について詳しく解説しています。
苦しい思いを一人で抱え込まずに、支援機関を活用して専門的なアドバイスを受けるようにしましょう。
コロナ禍の影響でDV相談件数が増えている

配偶者または交際相手からの度重なる暴力(Domestic Violence:DV)に悩む方からのDV相談の件数が増加しています。
DVが増えている要因として、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う休業や失業による生活不安、外出自粛や行動制限などによる社会的ストレスがあると見られています。
DV相談件数は毎年10万件以上で推移している
下表は、全国に設けられている「配偶者暴力相談支援センター」でのDV相談件数の統計と、2020年から内閣府男女共同参画局が実施した「DV相談+(プラス)」の統計を集計したものです。
<DV相談件数の推移>
| 年 度 | DV相談件数 |
|---|---|
| 2019年 | 119,276件 |
| 2020年 | 182,188件 |
| 2021年 | 176,967件 |
| 2022年9月現在 | 14,571件 |
2021年度のDV相談件数は2020年度よりわずかに減少ですが、その前年度の2019年の件数に比べると約58,000人増加しています。
DV相談の件数が10万件を超えるようになったのは2014年(平成26年)からで、それ以降2018年までDV相談件数に大きな増減は見られません。しかし、2020年以降は毎年10万件台後半の相談件数で推移しており、コロナ禍によるDV被害の大きさが浮き彫りになりました。
最もDV相談の件数が多い年齢と相談内容は?
DV相談者の年齢は30代が28.2%で最も多く、性別では女性が80%近くを占めています。次いで年齢は40代が26.4%、50代が20.6%、10代と20代が16.7%、年齢不明8.1%となっています(2021年度)。
相談内容で最も件数が多いのは、人格を否定するような暴言を吐く精神的暴力で約63%を占め、殴る蹴るの身体的暴力が28%と続いています。
そのほか、お金を自由に使わせない経済的暴力、嫌がる性交渉を強要する性的暴力、嫉妬心から友人や同僚との人間関係などをすべて断たせようとする社会的暴力に苦しんでいるという相談件数も少なくありません。
配偶者へのDV行為で逮捕される件数も増えている

以前は「DVは夫婦間のもめごとで事件ではない」と考えられていて、警察は通報があってもよほどのことがない限り立ち入ることはありませんでした。
しかし、被害者やその子供が負傷するニュースや記事が続いたことから、DVは犯罪行為を含む重大な人権侵害であるとして、2001年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV防止法)」が制定されました。
DV防止法では「配偶者からの身体的暴力を受けている者を発見した者や医療従事者は、警察または配偶者暴力相談支援センターに通報するよう努めなければならない」という情報提供・通報の努力義務が定められました(DV防止法第6条)。
警察官は、通報などによりDV行為が認められれば暴力行為の制止、現行犯逮捕、事情徴収、被害者の保護、支援機関についての情報提供などをするよう努めなければならないと定められています(DV防止法第8条)。
このようにDV防止法の制定によって、警察も通報を受ければ駆けつけて逮捕・拘留するなど、積極的に介入するようになったのです。
DV行為で検挙件数が多いのは暴行罪や傷害罪
2021年に警察庁が発表した検挙状況によると、刑法犯で検挙した件数が8,634件となっています。
罪種別では、最も多い件数が暴行の5,230件、次が傷害の2,509件。殺人に至った事件は2件、殺人未遂事件は108件もありました(警察庁「令和3年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」より)。
DV加害者に共通する特徴がある?

DV加害者のほとんどは男性です。加害者に共通するのは、外見的には礼儀正しくて人当たりがよいため「いいご主人ね」と思われるタイプであることです。
しかし、内面では妻を支配することで自分の心の安定を得ようとする、古い男尊女卑の考え方が残存していると分析する専門家もいます。
そのため、加害者は自分がDVをしているという認識はなく、むしろ「言うことに従わない妻に我慢している」と被害者意識を持つことさえあります。
一方、被害者(妻)のほうもDVをされているという自覚がなく、「私はいつも夫を怒らせてしまう」と加害者意識を持つ人が少なくありません。
ただ、現在は声を上げる女性が多くなってきていることから、第三者に相談して、そこで自分が受けていたのはDVだったことに気づくというケースが増えています。
もし、自分はDVの被害者かもしれないと思ったときは、1日も早く以下に紹介するDV相談機関を利用することをおすすめします。
DV相談に対応している全国の支援機関

DV防止法に基づいて、DV相談ができる支援機関や施設が全国に開設されています。まず、どこに相談すればよいかわからないという被害者向けに設けられたDV相談窓口から紹介していきます。
相談機関を案内してくれる内閣府の「DV相談ナビ#8008(はれれば)」
内閣府男女共同参画局では、DVのさらなる増加・深刻化を踏まえ、2020年からDV相談事業を開始しました。その1つが「DV相談ナビ」で、配偶者からの暴力に悩んでいる方のために、全国共通の電話番号「#8008(はれれば)」を設置しました。
「#8008」に電話をすると、発信地から最寄りの「配偶者暴力支援相談センター(後述)」に自動的に転送され、直接DV相談をできる仕組みになっています。
なお、「DV相談ナビ」は一般の固定電話と同じ通話料がかかります。また、相談できる時間は支援相談センターの受付時間内に限られる点にも注意が必要です。
電話:全国共通の短縮番号#8008
電話やメールで24時間相談できる「DV相談+(プラス)」
同じく内閣府が実施している「DV相談+(プラス)」では、電話とメールでのDV相談は24時間、チャットでは12時から22時までの10時間、DV相談を受け付け、専門の相談員が暴力について一緒に考えてくれます。そのほか、下記の支援も行っています。
- 同行支援(民間の支援団体と連携して直接支援する)
- 保護(一時的にホテルや民間シェルターなど宿泊施設を提供する)
- 外国人向け相談(対応語は英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語など。自治体によって対応語の数は異なる)
電話:0120-279-889(つなぐ・はやく)
メール・チャットはこちらから:https://soudanplus.jp/
DV支援の中心的機関「配偶者暴力相談支援センター」

都道府県に設置されている女性サポートセンターや男女共同参画センター、児童相談所、福祉事務所などに「配偶者暴力相談支援センター」が置かれ、DV被害者を支援する中心的な機関として対応しています。
被害者がDV相談していることを第三者に知られることのないよう、相談員は守秘義務に徹しているので安心です。
配偶者暴力相談支援センターでは、下記のような支援を実施しています。
- 専門機関の紹介
- カウンセリング
- 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護
- 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
- 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
- 保護命令制度(接近禁止命令など、裁判所が被害者の申し出によって加害者に命令を発する制度)の利用についての情報提供その他の援助
配偶者暴力相談支援センターの所在地一覧はこちら
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf
警察では「#9110」でDV相談に対応している
警察には、ストーカーやDV相談など事件に関連する相談をしたいときに使用できる専用電話「#9110」が設置されています。
全国共通の「#9110」に電話をすると、発信地を管轄する警察本部の相談窓口につながり、専門の相談員が対応する仕組みになっています。
警察が受理したDV相談件数は、DV防止法の施行日(2001年10月13日)より毎年増加しており、2020年度が82,643件、2021年度が83,042件で、DV法施行後最多の件数となっています(警察庁「令和3年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」より)。
#9110はあくまでも相談窓口です。暴力を振るわれたり刃物を突き付けられるなど、身の危険を感じるときは緊急通報ダイヤルの110番通報します。距離的に可能であれば警察か交番、駐在所に駆け込むようにしてください。
警察相談専用電話「#9110」
受付時間:平日の午前8:30~午後5:15(各都道府県警察本部で異なる)
なお、通話料は利用者負担となります。
以上の他にもDV相談窓口を設けているところは弁護士事務所や精神科クリニック、民間のNPO法人など数多くあります。いずれもDV被害者が苦痛から解放され、穏やかな日々を取り戻せるよう、さまざまな支援を行っています。
DVで別居・離婚を考えている方はNPO法人よつばにご相談を!

DV相談者が別居・離婚に踏み切れない理由の1つが、別れたら生活していけないという経済面での不安です。
別居すれば「婚姻費用の分担請求権」を行使して収入の多い方から生活費をもらうことは可能です。
しかし、相手は応じなかったり大幅な減額を要求することが多く、その場合は家庭裁判所に調停の申し立てを行うことになります。このようなときも弁護士を立てて交渉してもらえばスムーズに解決を図ることが可能です。
離婚となると、財産分与はじめ子供の親権や養育費など、法律的な知識を必要とする問題がたくさんあります。
離婚をする際に不利にならないよう、交渉のプロである弁護士に依頼することを検討してみましょう。弁護士を味方につければ精神的ストレスからも解放されます。
どのような弁護士に依頼すればよいかわからないという方は、「NPO法人よつば」の無料相談にお電話ください。
よつばでは、DV相談者に専門のカウンセラーが対応してお話を伺い、離婚に詳しい信頼できる弁護士の紹介も行っています。
DV相談者のほとんどが深い心の傷を負っています。そのため、カウンセラーはメンタルケアにも重点を置いてサポートしています。
よつばは、ボランティアで活動しているので料金は一切かかりません。無料相談は年中無休で受け付けていますので、悩みを一人で抱え込まずにいつでも電話相談をご利用ください。