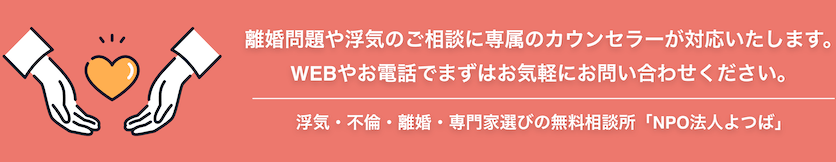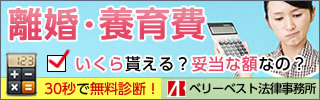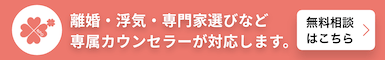離婚を決意してから新生活をスタートするまでの「決めることリスト」について
離婚を決意するまでには、様々な葛藤や不安があるものです。
しかし、一度決断したからには、前を向いて新しい人生をスタートさせるための準備が必要です。
離婚に伴う手続きや、生活環境の変化など、決めることは多岐にわたります。
この記事では、離婚を決意してから新生活をスタートするまでに、何を決め、どのように進めていくべきかを「決めることリスト」に沿って詳しく解説します。
まずは気持ちを整理しよう

離婚を決意するには勇気が必要です。
しかし、その決断に至るまでには、さまざまな感情が入り混じっているはずです。
怒り、悲しみ、不安、そして迷いなど。これからのことを考えるためにも、まずは自分の気持ちを整理することから準備を始めましょう。
離婚の理由を明確にする
離婚を決意した理由を明確にすることで、自分の気持ちを整理しやすくなります。
相手との価値観の違い、コミュニケーション不足、信頼関係の崩壊など、具体的な理由を挙げてみましょう。
自分の気持ちに正直になり、離婚に至った経緯を振り返ることで、今後の人生について前向きに考えられるようになります。
離婚後の生活をイメージする
離婚後の生活をイメージすることは、気持ちの整理に役立ちます。
新しい住まい、収入や支出の変化、子どもとの関係性など、具体的にイメージを膨らませてみましょう。
不安な点もあるかもしれませんが、新しい生活への希望を持つことが大切です。
離婚は人生の終わりではなく、新たなスタートであると前向きに捉えることで、気持ちが晴れやかになるはずです。
離婚をする場合に決めることリスト
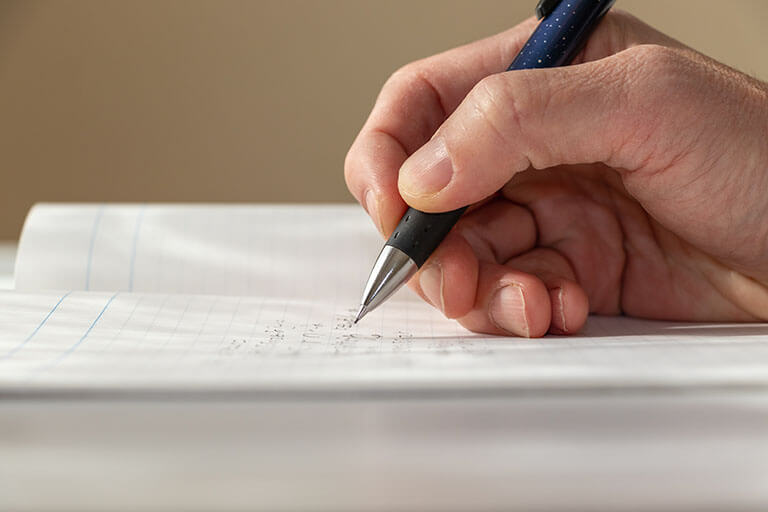
離婚を決意したら、次のステップとして具体的に決めるべきことや準備がいくつかあります。
離婚協議では、子どもの親権や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料など、重要な事項について話し合う必要があります。
また、離婚後の生活設計や手続きなど、確認しておくべきポイントも多岐にわたります。
円滑に離婚を進め、新しい人生をスタートするためにも、決めるべきことをリスト化し、優先順位を付けて整理していきましょう。
子どもの親権と面会交流
離婚をする際に、子どもがいる場合は親権者を決める必要があります。
親権者は、子どもの養育、教育、財産管理などの権利と義務を持ちます。子どもの幸せを最優先に考え、話し合いましょう。
また、親権者に決定されなかった親の場合は、面会交流の方法を決めることが大切です。
子どもの成長にとって、両親との関わりは重要です。子どもの年齢や状況に合わせて、面会交流の頻度やルールを決めましょう。
柔軟な対応を心がけ、子どもにとって最善の方法を見つけてください。
養育費
離婚後、親権者が子どもを養育するための費用が養育費です。
子どもの年齢や人数、親の収入や資産状況などを考慮して、適切な金額を決める必要があります。
養育費の目安は、子ども一人につき月額3〜5万円程度と言われていますが、あくまで目安です。
支払い方法は、毎月の定期支払いが一般的ですが、一括払いや物品での支払いなど、柔軟に決めることもできます。
養育費の取り決めは、子どもの幸せと健やかな成長を第一に考え、話し合いを重ねることが大切です。
婚姻費用
離婚が成立するまでの間、夫婦の生活費や子どもの養育費を婚姻費用と呼びます。
離婚が決まっても、正式に離婚が成立するまでには時間がかかるため、その間の生活費について取り決めをしておく必要があります。
婚姻費用は、夫婦の収入や生活水準、子どもの有無などを考慮して決定します。
支払い方法や期間についても、双方が納得できるように話し合いましょう。
婚姻費用の取り決めは、離婚協議の中でも重要な項目の一つです。円滑に離婚を進めるためにも、早めに話し合いを始めることをおすすめします。
慰謝料
離婚の際、慰謝料の請求が発生する場合があります。
慰謝料とは、離婚の原因を作った側が、相手方に対して支払う精神的な損害賠償のことです。
不貞行為や暴力、酷い借金などが原因で離婚に至った場合、慰謝料の請求が認められる可能性が高くなります。
慰謝料の金額は、離婚の原因の程度、婚姻期間、子どもの有無など、様々な要因を考慮して決定されます。
話し合いで決められない場合は、調停や裁判で決めることもあります。
慰謝料の取り決めは、双方の感情も絡むデリケートな問題です。冷静に話し合い、合意点を見出すことが大切です。
年金分割
離婚する際、年金分割について取り決めをしておくことが重要です。
年金分割とは、夫婦の婚姻期間中に納めた厚生年金を、離婚後に分割して受け取る制度のことです。
分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金のみで、国民年金は含まれません。
年金分割を希望する場合、離婚後2年以内に手続きを行う必要があります。
分割割合は、婚姻期間や子育てへの貢献度などを考慮して決められます。
年金分割は、離婚後の生活設計に大きく影響するため、よく話し合い、理解を深めておくことが大切です。
離婚手続きの流れと必要な手順

離婚を決意したら、次は具体的な手続きを進める段階です。
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。最も一般的な協議離婚は、夫婦の合意があれば比較的簡単に手続きを進められます。
一方、調停離婚や裁判離婚は、話し合いでの合意が得られない場合に選択される方法です。
離婚手続きを円滑に進めるためには、それぞれの方法の流れと必要な手順を理解しておくことが大切です。
ここでは、各離婚方法の手続きの流れを詳しく説明します。
協議離婚の場合の手続き
協議離婚は、夫婦双方の合意があれば成立する離婚の方法です。以下の手順で進めます。
- 離婚の合意:夫婦で話し合い、離婚の意思を確認し合います。
- 離婚協議書の作成:離婚の条件(親権、養育費、財産分与など)を離婚協議書にまとめます。
- 離婚届の準備:離婚届に必要事項を記入し、夫婦双方が署名・捺印します。
- 離婚届の提出:離婚届を夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
- 離婚届受理証明書の取得:離婚届が受理されたら、受理証明書を受け取ります。
- 離婚後の手続き:氏名変更、住民票の変更、子どもの戸籍の変更などの手続きを行います。
協議離婚は、裁判所を介さずに手続きを進められるため、比較的簡単に離婚できる方法です。
ただし、離婚の条件について夫婦で合意している必要があります。
調停離婚や裁判離婚の流れ
調停離婚や裁判離婚は、夫婦の合意が得られない場合に選択される方法です。弁護士に相談し、適切な方法を選ぶことが大切です。
それぞれの流れを確認していきます。
調停離婚の流れ
調停離婚は、夫婦の話し合いで離婚の合意が得られない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の立ち会いのもと、離婚条件について協議を進める方法です。
調停が成立した場合は、調停調書に基づいて離婚届を提出します。ただし、合意に達しない場合は、調停不成立となります。
- 調停の申し立て:夫婦のどちらかが、家庭裁判所に調停を申し立てます。
- 調停期日の通知:家庭裁判所から、調停期日の通知が届きます。
- 調停の開始:調停委員立ち会いのもと、話し合いを進めます。
- 調停成立または不成立:合意に達した場合は調停が成立し、調停調書が作成されます。合意に達しない場合は、調停不成立となります。
- 離婚届の提出:調停が成立した場合、調停調書に基づいて離婚届を提出します。
裁判離婚の流れ
裁判離婚は、調停離婚で合意に達しない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する方法です。
裁判官の主導で、双方の主張を聞き、証拠調べを行い、判決が下されます。判決が確定したら、その内容に基づいて離婚届を提出します。
裁判離婚は、調停離婚よりも時間と費用がかかるデメリットがあります。
- 離婚訴訟の提起:調停不成立の場合、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
- 訴状の送達:裁判所から、相手方に訴状が送達されます。
- 答弁書の提出:相手方は、答弁書を裁判所に提出します。
- 弁論の開始:裁判官の主導で、双方の主張を聞き、証拠調べを行います。
- 判決:裁判官が判決を下します。
- 離婚届の提出:判決が確定したら、判決に基づいて離婚届を提出します。
離婚後の氏名変更や住所変更の手続き
離婚が成立したら、氏名や住所の変更手続きが必要になります。
離婚後の手続きは、離婚の方法によって異なる場合があるため、手続きに不明な点がある場合は、市区町村役場や法務局に問い合わせると良いでしょう。
氏名変更
氏名変更の手続きは、離婚届を提出した市区町村役場で行います。
離婚前の氏に戻す場合は、離婚の日から6ヶ月以内に届け出る必要があります。
必要書類は、離婚届受理証明書、戸籍謄本、印鑑証明書などです。
住所変更
住所変更の手続きは、新しい住所地の市区町村役場で行います。離婚後2週間以内に、新しい住所地に転入届を提出します。
必要書類は、離婚届受理証明書、戸籍の附票、印鑑登録証明書などです。
また、子どもの戸籍の変更手続きも必要です。
親権者が子どもの戸籍を管理することになるため、親権者の氏と住所に変更します。
手続きは、親権者の本籍地または住所地の市区町村役場で行います。
離婚後の生活設計のために決めることリスト

離婚が成立したら、新しい生活に向けて様々な準備が必要になります。
離婚後の生活を安定させ、新しい人生をスムーズにスタートするためには、収入の見直し、住まい、子どもの養育環境の整備などについて綿密に計画を立てることが大切です。
ここでは、離婚後の生活設計で決めることリストを紹介します。優先順位を付けて、一つずつ確実に進めていきましょう。
住まいの確保と引っ越しの準備
離婚後、新しい住まいを確保することは生活設計の中でも優先度の高い事項です。
離婚前から、予算や希望する地域、部屋の広さなどを考慮して、物件探しを始めましょう。
賃貸物件の場合は、敷金・礼金や仲介手数料などの初期費用も計算に入れておく必要があります。
住まいが決まったら、引っ越しの準備を進めます。
引っ越し業者の手配、必要な家具・家電の購入、子どもの学校や保育園の手続きなど、事前に計画を立てて着実に進めていくことが大切です。
また、住所変更の手続きも忘れずに行いましょう。
収入と支出の見直し
離婚後は、収入と支出の構造が大きく変化します。
特に、シングルインカムになることで、収入が減少する一方、生活費の負担は増加することが予想されます。
離婚後の生活を安定させるためには、収入と支出の見直しが不可欠です。
まず、収入面では、自分の収入源を確認し、安定した収入を確保できるよう努めましょう。
離婚に伴う財産分与や養育費、慰謝料などの収入も考慮に入れます。
次に、支出面では、固定費と変動費を見直し、無駄な出費を削減することが大切です。
住居費、光熱費、食費、子どもの教育費など、優先順位をつけて支出を管理しましょう。
収支バランスを取るために、必要に応じて副業や資格取得にチャレンジするのも一つの方法です。
子どもの養育環境の整備
まず、子どもの気持ちに寄り添い、離婚に伴う環境の変化に適応できるよう、十分なケアを行うことが大切です。
子どもが安心して過ごせる居場所を確保し、日常生活のリズムを維持できるよう配慮しましょう。
次に、教育面では、子どもの年齢や発達段階に合わせた適切な教育環境を整える必要があります。
学校や保育園、塾などの選択、教育費用の負担など、具体的な計画を立てましょう。
子どもの養育環境の整備は、離婚後の生活設計の柱となる事項です。子どもの幸せを第一に考え、慎重に計画を立ててみて下さい。
シングルライフを充実させるヒント
離婚後は、シングルライフを前向きに捉え、自分らしい生活スタイルを確立することが大切です。
まず、趣味や興味のあることに積極的に取り組んでみましょう。
新しい習い事を始めたり、海外旅行に挑戦したりと、自分の世界を広げることで、充実感を得ることができます。
また、友人や家族との交流を大切にすることも重要です。離婚後は、周囲のサポートが心強い味方になります。
さらに、自分の時間を有効に使い、自分磨きに励むのもおすすめです。
運動やスキンケアなど、自分の心と体の健康に投資することで、自信を取り戻すことができます。
シングルライフは、自分と向き合う大切な時間です。前向きな姿勢で、充実した日々を送ることを心がけましょう。
記事まとめ

この記事では、離婚を決意してから新生活をスタートするまでに、夫婦で話し合うべき「決めることリスト」と、どのように進めていくべきかを解説しました。
離婚後の生活を再構築するためには、様々な準備と決断が必要です。
子どもの親権や養育費、財産分与など、離婚に伴う条件を話し合うことから始まり、新しい住まいの確保、収入と支出の見直し、子どもの養育環境の整備など、生活のあらゆる面において計画を立てなければなりません。
大切なのは、離婚を人生の終わりではなく、新たなスタートと捉えること。
前を向いて、一つずつ着実に準備を進めていきましょう。シングルライフを充実させるヒントを参考に、自分らしい生活スタイルを見つけてください。